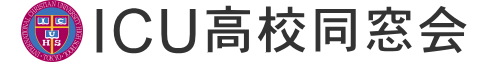『ぬるい缶コーヒー、あるいは混沌とした冷蔵庫の話』
エッセイ・リレーのバトンというものが、どういうわけか僕のところに回ってきた。陸上の選手が握るような、つるりとした流線形のそれを想像していたけど、実際に手渡された感触は少し違う。夜中の高速道路のパーキングエリアで、見知らぬ長距離トラックの運転手から「これ、よかったら」と無言で差し出された、ぬるい缶コーヒー。そんな感じに近い。熱くもなく、冷たくもない。でも、悪くない。
その缶コーヒーを渡してくれたのは稲岡美紀さん。稲岡美紀さんからバトンを受け取りました。あの、口先をちょっと尖らせて、的確に世界を斜め四十五度から切る人。『Olive』のページから抜け出してきたみたいで、でも笑うと急に人懐っこい。そんな稲岡さん、僕は結構好きです。
14期生で、高校三年間ずっと二組にいた須藤格です。
自分の育った場所の話をしようとすると、いつも少しばかりややこしい。フランスで六年間を過ごし、日本に戻って小学校の途中から卒業まで。そして中学時代は韓国で、また日本へ。それはまるで、毎回新しいパラシュートを背負って、見知らぬ街角にふわりと降り立つような日々だった。まず方角を確かめ、その土地の暗黙のルールを学び、言葉を(まあ、そこそこに)身につける。ようやく自分の足でしっかりと地面を踏みしめた、と感じる頃には、また次の風が吹いてくる。
1991年、その風は僕をICU高校に運んだ。
足を踏み入れてみると、そこは不思議な四層構造のカクテルのようだった。いちばん上には、英語圏からの帰国生であるL1組がきらきらと輝いている。彼らが廊下をすり抜けていくと、まるで『ビバリーヒルズ高校白書』の登場人物たちみたいに、軽やかな英語の響きが残った。いちばん下には、日本の土壌にしっかりと根を張った国内生がいる。彼らは場の空気の読み方に迷いがない。そしてその間に、非英語圏からの帰国生や、僕のようなJ枠の生徒たちが混ざり合った、少しばかり濁った層が存在する。味は悪くない。ただ、輪郭が少し曖昧で、自分の居場所がどこなのか、ときどきぼんやりと霞んでしまう。
でも、そのカクテルは、誰かがかき混ぜるでもなく、絶妙なグラデーションを描いていた。そんな場所でできた友人というのは、なぜか長持ちするらしい。三十二年という時間が過ぎた今でも、ときどき僕らは顔を合わせる。そして、当時のどうしようもなかった話から、今の仕事や子育て、家族のあれこれまで、まるで昨日の続きみたいに、何のてらいもなく話すことができる。時間は、ときに優秀な編集者の役割を果たしてくれるのだなと思う。
近頃、「多様性」とか「包摂性」とか、そういう言葉をよく耳にする。ずいぶん便利に都合よく使われているし、僕自身使っている。けれど僕らのいた頃のICU高校は、そんな標語が掲げられるよりずっと先に、ただ日常が動いていたような気がする。
あれは巨大なシェアハウスに置かれた、一台の冷蔵庫だったのではないか、と今になって思う。ドアを開けると、カマンベールチーズの隣に真っ赤なキムチが陣取り、納豆の隣にはスキッピーのピーナッツバターがでんと構えている。ときどき匂いが混ざり合って、おや?と思うこともある。でも、誰もそれらの食材を無理やり一つの鍋に放り込んで、「統一記念スープ」みたいなものを作ろうとはしなかった。大事なのは、多種多様な食材が、同じ冷蔵庫に収まっているという事実そのものだった。必要なときに、それぞれが静かにそれを取り出して、自分の皿に載せればいい。そうしているうちに、キムチとチーズを一緒に食べると案外いける、なんて発見もあったりする。たぶん、そういうことだったのだと思う。
誰かにやみくもに受け入れられることの先には、自分の足で立つ、ということがある。それぞれの人間が、それぞれの歩幅で、同じ道をみんなで歩いていく。無理に足並みを揃えようとすれば、かえって転んでしまう。周りの雑音はBGMくらいに聞き流して、ただ前を見て共に進む。
僕は今、教育行政に関わる仕事をしているけれど、あの混沌とした冷蔵庫の記憶は、意外なほど役に立っています。壁に新しいルールを貼り出すよりも、静かに冷蔵庫のドアを開けて、中身をそっと確かめるほうが、物事はうまくいく場合が多い。
気がつけば、50歳。それはまるで、賑やかなパーティーの途中で、ふと音楽が止み、部屋が静かになったことに気づく瞬間に似ている。壁の時計が針を刻む音が、以前より少しだけ大きくはっきりと聞こえる。
あとに来る人たちのために、何か役に立つものをテーブルの上に残しておけたらいいな、と思う。でもそれは、立派な教訓なんかじゃなくて、面白い話とか、まあまあ悪くないパスタのレシピとか、きっとそういう種類のものだ。手帳の空白は少しずつ貴重品になっていくけれど、不思議と歩幅は落ち着いてくる。僕らのつけた足跡が、次の世代にとってのささやかな目印になれば、それで十分だ。立派に舗装された道は作れなくても、道端の石ころを二つ三つ、脇にどけておくことくらいなら、まだできるかもしれない。
というわけで、このぬるい缶コーヒーを次の誰かに回す時間だ。バトンは、親愛なる西村真理子さんへ。彼女なら、冷蔵庫の中身をもう少し上手に整理するだろうし、道の石ころをどけるだけじゃなく、その場所に座り心地のいいベンチを置く方法を知っているに違いない。次のページからも、きっと心地よい音がするはずです。