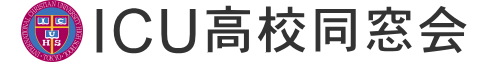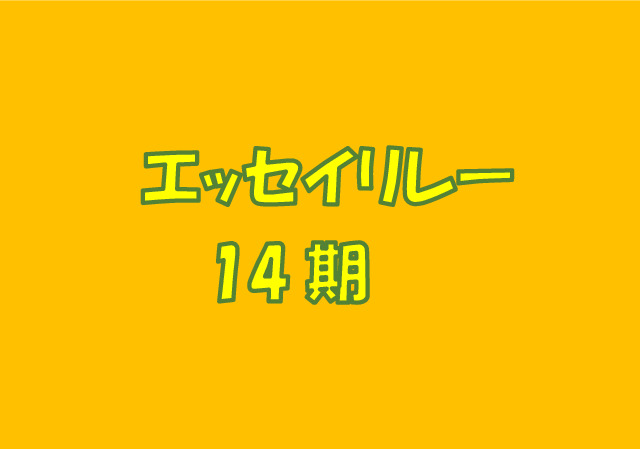先日実家に帰り本棚を整理していたら、懐かしいものを見つけた。
1993年4月の沖縄修学旅行記念文集だった。読みだすと止まらなくなり、ページをめくっていると忘れていたあの時の風景や思い出が蘇ってきた。
戦争のこと、海や自然のこと、友達との思い出。みんなの感想は様々で、私の感想は沖縄の文化に関するものだった。
「人の良さそうなおじさんが三味線を奏でながら安里屋ユンタを披露してくれました。あの音色は今でも耳に残っています。」
「石垣島では、ミンサー織りと呼ばれる織物の話を聞きました。昔、女の人が愛する男の人の為に長い時間をかけて織り、それに自分の想いを託したそうです。その1つ1つの模様にもきちんと意味が込められていて、なるほどと感心させられました。」
「沖縄料理もいろいろ味わうことができました。肉や油をたくさん使っているのにさっぱりとしていて飽きのこない味。料理教室ではジューシーと猪ムドゥチを作りました。」
どんなことを書いたのか全く覚えていなかったので新鮮な気持ちで読むと同時に、高校生の頃から興味の対象は変わっていないんだなぁと思った。もし今修学旅行に行ったとしても、やはり私はミンサー織や安里屋ユンタのことを感想文に書くだろう。
3年前、コロナ禍で趣味の旅行も行けなくなった時期に、ふと目に留まった着付教室のポスターがきっかけで着付を習い始めた。着物を着るようになって特に心惹かれたのが沖縄の織物や染物だった。
ミンサー織、花織、紅型。沖縄の布は色が鮮やかなもの、沖縄の生活や自然をデザインしたものが多く、身に着けていると心が弾む。
沖縄の着物や帯がきっかけで沖縄工芸展などに行くようになり、そこで出逢ったのが三線。老後の趣味に良さそうだと思い、去年の秋から習い始めた。
三線は文字通り三本の弦があり、ツメ(バチ)を右手に持って弾く。自分の爪で弾く人もいる。琉球音階は「レ」と「ラ」が無いドミファソシド。この独特な音階と、沖縄の言葉ウチナーグチの歌詞、そしてテントンテンというかわいらしい音色は一瞬にして心を沖縄へといざなってくれる。
竹富島で水牛車に揺られながら聴いた安里屋ユンタを弾けるようになり、旅行で訪れた沖縄の民謡居酒屋やイベントなどで三線を弾くうちにますますのめりこむようになった。
今では三線が生活の中心となっている。早く仕事を辞めて、毎日三線を弾き歌いながら暮らすのが夢である。
沖縄の着物や帯を身にまとい、沖縄の楽器を奏で、沖縄の歌を口ずさみ、沖縄の料理を味わう。
気がつけば私の生活の中に沖縄がいっぱいあるのは、もしかしたら 美しいミンサー織や耳に心地よい三線の音色が修学旅行の楽しかった思い出とともに心の奥深くにずっと忘れられずに残っていたからなのかもしれない。
今日も仕事帰りのレッスンのため三線を背負って会社に行く。
本当はこのまま海にでも行って心ゆくまで三線を弾きたいのだけれど。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
まさか私に回ってくることはないだろうと思っていたエッセイリレーだけど、野球部マネージャー仲間の美絵から渡されたバトンなので喜んで受け取りました。
そしてこのバトンを修学旅行記念文集の集合写真で私の隣にいる石原裕子ちゃんにつなぎます。