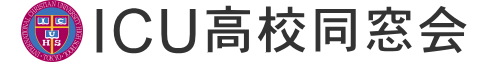喜多布由子からバトンを受け取った。器楽部の強烈なキャラクターたちをカラフルに描いた布由子のエッセイは, 40年以上前の日々を鮮明に思い出させてくれた。さすが物書きだ。
という私も広い意味では同業者。その割にはこの文章を書くのに妙に緊張している。理由は2つ。1つは私はこの春まで、30年以上報道記者をしていたこと。ひたすら他者の取材と事実の分析に基づいた記事を書いてきた。自分の個人的な意見や感想を書くことには慣れていないのだ。もう一つは私は英語で記事を書いてきたこと。もちろん友人や取材先とのメールのやりとりなどは日本語でもしてきたが、きちんとした文章を日本語で書くことはほとんどしていない。
日本で生まれ育った私が、アメリカの新聞の記者として東京、ニューヨーク、ワシントンDCで長年働くという珍しいキャリアをたどることになったのには、ICU高校での経験が大いに関係している。
小さい頃から海外に住むことに憧れていた私は、第一志望で創立4年目のICU高校に一般生として入学した。中学時代に猛烈に英語を勉強したせいで、帰国子女向けの英語のクラスに配属されたのは良かったが、最初は苦労した。いきなりペーパーバックでジャック・ロンドンの短編小説をを読まされ、辞書を片手に泣きながら宿題をした日もあった。おかげで2年生の秋に交換留学でアメリカの高校に通い出した時には、サリンジャーやヘミングウェイの小説が何とか読めるようになっていた。これまで英語はどうやって勉強したのと聞かれると、沢山活字を読みましたと言ってきた。
とは言え、自分の英語力にはいつも不満、不安を感じていた。ICU高校では休み時間に、気になる男子の噂話を英語でする帰国子女の友人たちの会話が理解できずに落ち込んだ。彼らの子供の頃のハロウィーンやサマーキャンプの思い出話が羨ましかった。完璧な英語でバラードを歌う北代桃子は別世界の人のようだった。「私は帰国子女じゃないし」というコンプレックスはその後もずっと引きずった。社会人になって、海外の報道機関で英語で記事を書きながらも、仕事がうまくいかないと「私は帰国子女じゃないし」と落ち込んだ。
それをやっと克服したのは40代に入った頃だったと思う。通信社でニューヨーク勤務の後、ウォール・ストリート・ジャーナルの東京特派員として久し振りに日本に戻った。日本、アジア各地を取材して周り、次から次へと記事を書いた。ふと気がつくと、プロの英語の世界に20年も身を置いていた。高校時代の帰国子女の仲間は、海外生活は長くても10年ぐらいだった。もう帰国子女コンプレックスは卒業だと思った。
今回はワシントンに住んで10年近くになる。夫も2人の子供達もアメリカ人。健康保険や年金もアメリカのものしかない。しばらく前に意を決してアメリカの国籍も取った。日本に帰ると違和感を覚えることも増えている。それでもICU高校の友人たちはいつ会ってもしっくりと語り合える大切な存在だ。