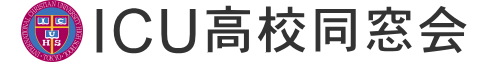15歳、1年3組、右から2列目の、前から2番目。
後ろを振り向いたときに、隣の列の後ろから2番目の自分の席で立っていたあなたと、初めて目があった瞬間。今でもわたしは切り取られた写真のように記憶しているけれど、あなたは入学式のその日に話したことを覚えていないという。次の4月であの日から15年、これからは出会ってからの時間の方が長くなっていくのに、最初を覚えていないなんてバトンを繋いでくれた相棒も薄情である。渡されたバトンのエッセイを拝見するに、彼女は味を記憶する人間で、わたしは景色を記憶する人間のようなので致し方ない。
いくつもの瞬間を、写真のように記憶している。3階の廊下から見下ろした中庭。親友と寝転んだ高跳びのマット。第二女子寮のカーテン。校庭の空を分断する電線。日記をつけていなかった3年間は景色で心に残り続けている。
去年高校の学園祭で森に足を踏み入れた瞬間の、背筋に走った感触は、懐かしいという言葉にはおさまらない。押し入れの一番奥に仕舞い込んでいた、そこにあることは分かったまま、目に触れることなくセピア色に焼けていった写真が突然焼き直されて極彩色で現れた。ああここで、わたしは3年間を過ごしたのだ。好きなように、過ごさせてもらったのだ。
ある年の同窓会の郵送物の中に、「この高校を卒業したら、どんな困難も乗り越えられる」という一郎校長のメッセージが入っていた。森にすべての困難があったのではない。大きな秩序と倫理観を保ちながら、自分と他者を切り分け、侵害せずにいることが当然として通っていた。そういう考えもあるんだね、だけど僕はこう思ったよ。そのままの自分であることを許容された場所という森の記憶が、許しがあったという記憶が、自分の中のどこかにあり続ける限り、どんな困難も超えていくのだろう。森に帰れば、森にいたときに、わたしはそこにいたという許しが、わたしを支え続ける記憶なのだろう。
29歳、至極真面目に生きている。大学を卒業し、就職し、肩を叩かれそうになく8年目に突入した真面目なサラリーマンである。真面目な今と、暴走機関車のようだった3年間がかけ離れている。何もできず鬱屈とし、足踏みばかりしてしまう29歳のわたしを、叶うならば15歳のわたしに見てほしい。そんなのわたしじゃないって、叱り飛ばしてほしい。そんな時を超える魔法の金平糖の話を、4号室のルームメイトに読ませてもらった気がする。
次のバトンはきっとわたしのことはお見通しの友人に渡そう。27歳の七輪の夜はありがとう。10年サイクルな気がするので、次は37歳を迎えたらだと思っていてほしい。繋がったバトンで、素敵な言葉を待っている。