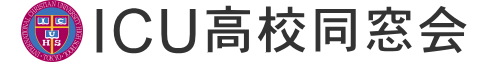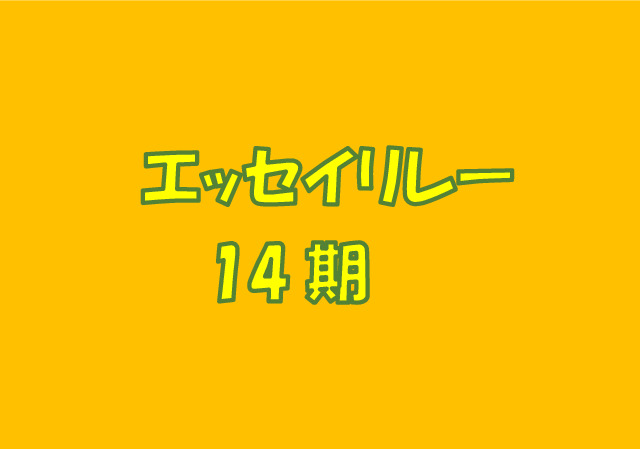「福所さんって、帰国子女っぽくないよね」
最近、コロナ禍のオンラインコミュニティで知り合った友人と初めてリアルで会った時に言われた言葉。(そもそも、もう帰国“子女”という年齢ではない、というツッコミはさておき)どうやら私は、いわゆる帰国子女のイメージとは裏腹に、周囲の状況や場の空気をものすごく読もうとしているように映るらしい。
でも実はこの言葉、ちょっとデジャブでもある。高校時代も「しのって帰国子女っぽくないよね〜」って言われたっけ。
私は「J枠」で入学した。小1〜2でメキシコ(日本人学校)、小4〜6でアメリカ(現地校)、中1〜2でタイ(日本人学校)と、日本と海外を行ったり来たり。他の学校の帰国子女枠は「帰国して1年以内」という条件が多かったが、ICUHSだけは他の海外滞在歴も合算した上で帰国からの年数も考慮してくれた。高校受験への準備という点では一般生に近いわけだが、「帰国子女っぽくない」理由はそれだけではないはず。
幼少期に転校が多かったことで、その場になじめるポジショニングを観察する癖がついた、というのが一番もっともらしい理由だと思う。ただ、今回エッセイリレーを書くにあたってもう一つ気づいたことがある。それは、ICUHSでの巡り合わせが、逆説的だけど「空気を読む」にさらに磨きをかけたかもしれない?ということ。
それは1年生のクラスでのこと。「しのぶ」なんてさほどメジャーな名前ではないのに、クラスにはもう一人「忍」がいたのだ。経緯はもはや忘れてしまったが、クラスでは「忍」が「しのぶ」で、私は「しの」と呼ばれていた。
一件落着。めでたし、めでたし、と思ったら…。
なんと、14期には本名で「しの」がさらに二人(!)いたのである(今回バトンを渡してくれた、みわしのちゃんがその一人)。
2年生のクラス替えで学年全体がシャッフルされてみたら、「しの!」と声がして振り返ったら違った…orzということが頻発(まあ、「しの」が3人もいるとなれば無理もない)。加えて、部活で所属していたバスケ部では名前かぶりがなかったので、そちらではフルの「しのぶ」で呼ばれていて、「しの」と「しのぶ」の二刀流。ああ、ややこしい。
そんな事情で、「誰が」「どの程度の距離から」「しのorしのぶのいずれで」呼びかけているかを判断してリアクションする、ということをやってのけていたあの頃。一般的な空気を読むとはちょっと違うが、場の状況を読むアンテナは鍛えられたに違いない。
さて、そんな「場の状況を読む力」は結果的に、自分の力を発揮できそうな場所を探し当てる嗅覚にもつながったのではないかと思う。
例えば、進路選択では、入学当初は英語力を活かして…と思っていたが、ほぼネイティブな英語圏からの帰国生に圧倒され、これでは食べていけないかもと理系に進んだ。その後の紆余曲折は話すと長くなるのでこの場では割愛するが、現在は「理系出身、弁理士を経て、キャリアコンサルタントの…」と名乗るに至っている。
自分の力を発揮できる場所を探し当てる、というと聞こえはいいけれど、「現状に満足せず、別の何者かになろうとする」のと隣り合わせでもある。若い頃は伸び代もあり、社会人として自立する上でも恩恵を受けてきたけれど、このアドレナリン過剰なスタンスのままでは足りないピースを追い続けているようで落ち着かないこともある。
今年は50歳の節目ということで人生の折り返しに意識的になってみると、「背伸びしない、そのままの自分を受け入れる」という視点がもたらすセロトニン的な心の平穏にもしみじみとしてきたりして。
そこにきて、このエッセイリレー。
須藤くんやことやん(琴屋さん)の、「多種多様な食材が同じ冷蔵庫に収まっている」「みんなそれぞれだよねな温度感」という指摘。言われてみれば、確かにそうかも。
「別の何者かになろうとせずとも、そのままでOK」な場がこんなに近くにあったなんて。青い鳥、的な感覚がなんだかくすぐったくもある。
このエッセイリレーの音頭をとってくれた稲岡美紀さんをはじめ、バトンをつないでくれたみんなに感謝です。それぞれ素敵な気づきのあるエッセイをありがとう!
さて、そろそろ8月も最終日。果たして14期生のアンカーは誰に?