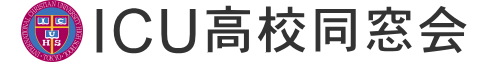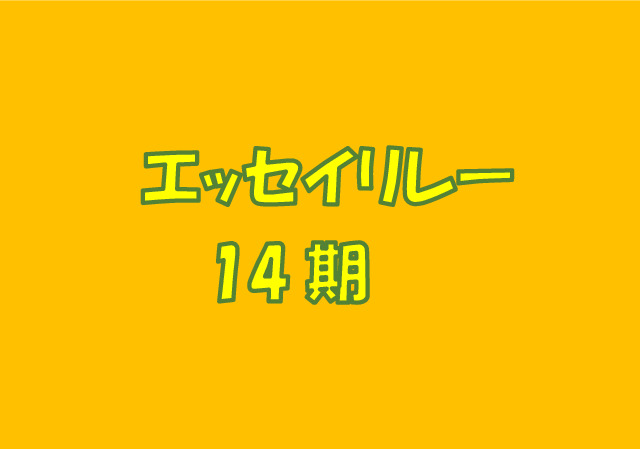最近、戦前の古書を入手して読むことに凝っています。狭い部屋に積みあがる古書の山に、妻は眉をひそめていますが、もともと理系人間のこの私が、何故古書を読むようになったのか。それは今から6年前に発覚した娘のカンニングがキッカケでした。
その日、いつも通り学校から娘が帰ってきたので、私は仕事の手を止め、娘のいる居間へと向かいました。貧乏暇なしで共働きの我が家では、平日の娘の宿題の確認は、自宅で仕事をしている私が担当でした。
一緒に連絡帳や配布物を読み合わせながら確認をしていると、ランドセルの中から算数のテストの答案用紙が出てきました。
見ると、我が子ながら目を覆いたくなる様な散々な出来映え。簡単な足し算・引き算が全く出来ていません。
娘の材料の半分は紛れもなくこの私。この世の残酷な業を感じつつも、半ば、哀れな娘への償いの様な心持ちで、算数の教科書とノートを広げ、一緒に復習を始めることにしました。
ところがです。
算数のノートを開くと、そこに書かれた練習問題の解答は、どれもこれも丸ばかり。非常に良く解けているのです。
不思議に思って原因を探っていくと…なんとノートの練習問題は「お友達の答えを写した」ことが判明しました。
「お友達に『見せて』って言ったの?」と聞くと、首を横に振ります。黙って盗み見たのです。紛れもないカンニングです。
「答えを写すのは卑怯なこと。卑怯なことはしてはいけない。」
「間違いは自分を成長させてくれる機会なんだから、ズルせず正々堂々と、自分の力で解いて来なさい。」
そう言って、その場は終わりました。が、仕事場に戻り、独りになると、静かにある思いがこみ上げてきました。
(ああ遂に、この時が来たか。
親として、いや、父として、
世の中の是非を、我が子に教えなければならない時が。)
しかしまた、こうも思いました。
(私のようなロクでもない人間が、
その場その場で目についたことを、行き当たりばったりで指導しても、
伝えられることなど、たかが知れている。
はてさて、どうしたものか。)
考えていても始まらないので、まずはとにかく国内外の育児・子育て書をあれこれ読み漁ってみました。
が、何というか・・・とにかく回りくどい。
主体性とか自己肯定感とか、そんなことばかりで、生ぬるい。性に合わない。
もっとこう、明快・簡潔に、抜け漏れなく伝える方法は無いものか。
そんな中、偶然手にしたのが、戦中の道徳教科書の復刻版である「修身」でした。
小学1年から6年まで各学年20課、合計120課という充実したコンテンツ。中身も「嘘はつくな」「時間を守れ」「物は盗むな」「友を助けよ」など基本はしっかり押さえてある。そもそも子供向けに書かれたものなので、挿絵つきで小学生の娘にはピッタリ。
さらに「教師用」なる指導書があることを知り探してみると、例として授業の台本が用意されている。早速これを読み聞かせてみたところ、なんと娘に大好評!「面白い。早く次の話が聞きたい」とまで言うようになりました。
しめしめ。
これに味を占めた私は、復刻版の戦時中の版では飽き足らず、大正期・明治期の古書を求め、古本屋やメルカリなどを漁るようになりました。特に「教師用」は入手が困難で、錦糸町にある「教科書研究センター付属 教科書博物館」に複写を求めて足を運ぶようにまでなってしまいました。
ここまでくると、もはや娘のためというよりも、自分の興味関心のため。仕舞いには高等小学校・高等女学校などの教科書・指導書も買い漁って、読みふける始末。
こうしてのめり込んで行く中で、ふと全体を俯瞰してみると、繰り返し現れるいくつかのキーワードがあることに気が付きました。博愛・公平・誠実など、いわゆる道徳的なものから、勇気・自立自営・公益など、そうではないものも含まれています。
「修身」とは現代で言う「道徳」の授業の前身ではなかったのか。かつての日本人が大切にしていた原理・原則とは、一体なんだろう。
(今思えば、自分の浅学に恥じ入るばかりですが)更なる散財を進めるうち、日本には12の徳目を記した『教育勅語』なるものがあることを40代にして初めて知りました。更にその元となる20の徳目を記した『幼学綱要』、最後にこれら2つの発布の契機となった『聖喩記』の一節に辿り着きました。
この聖喩記は、明治初期の天皇語録で、その一節に、急激に西洋化する中で、古い日本的なものを蔑み、新しい西洋的なものを崇拝する当時の帝国大学への憂いが記されています。
当時の帝国大学と言えば、日本の将来を担うリーダー達を育成する機関。
修身の授業の源流に「未来のリーダー達への想い」が通底していると知った時、いわゆる道徳的ではない徳目が繰り返し現れる理由が分かりました。
現代に目をやると「パワーポージング(=姿勢)」「やり抜く力(=勤勉・忍耐)」「コールドシャワー(=武士の気合い入れ)」「コンフォートゾーンを抜ける(=勇気・剛勇)」など、自己成長のために語られる多くの事柄は、日本人なら当たり前のように言われてきたことばかり。ようやく西洋が追いついてきたのではと思うことも多々あります。
そうか・・・修身とは、長い年月の淘汰を経て統計的に実証された、日本の成功哲学でありリーダーシップ論だったのか・・・
育児は育自。またひとつ、勉強になりました。娘よ、ありがとう。
そして、一般生理系男子のレアキャラの私が、グローバル人材の育成を掲げる我が母校を振り返ると、思うのです。一見、日本的な価値観とは掛け離れた校風の中で、博愛・公平・勤学・立志など、実は日本的な徳目を備えた良き仲間に溢れていたな、と。多感な高校3年間を良き仲間と過ごせたことは、今でも私の宝物です。
そんな仲間の一人、琴屋さんよりバトンを受け取りました。ありがとう。
そして仲間の一人、松本さんへとバトンを渡します。よろしくね。