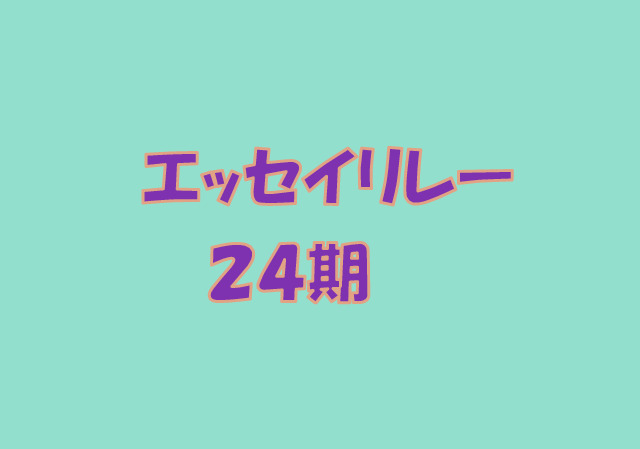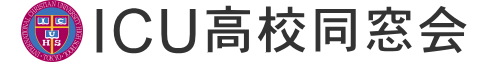二十四期の木矢(高柳)星歌です。前の執筆者の松岡(伊藤)千都さんは面白い虫や生き物を見つけると時折連絡をくれ、生物の話で盛り上がってくれます。
さて、ICU高校での3年間は楽しい思い出でいっぱいです。実家が群馬県で通うには遠かったので第二女子寮に入り、寮生活を楽しみました。自分から声をかけて友人関係を築くことが苦手だった当時の私としては、相部屋でルームメイトと過ごす時間が長かったり、寮生同士で頻繁に会話が発生したりする寮の環境はありがたいものでした。引っ込み思案な私が何も口に出さずに座っていても受け入れてくれ、たまに言葉を発すると真剣に耳を傾けてくれた友人たちのおかげで、社交性が未熟だった私は「人と話すのって楽しいんだなあ」という何ともシンプルな結論に到達し、その後の人生において他人との関わりに積極的になれたように思います。
ICU高校の先生方とも多くの思い出があります。2、3年生の時に担任していただいた高柳先生とは授業外でお話しする機会があり、ファンタジー小説、特にミヒャエル・エンデの小説や、ル=グウィン作のゲド戦記の話題で盛り上がりました。「沖縄の昔の船には目が描いてある」という先生のお話に、「ゲド戦記に出てくるのと同じ!」と興奮したのを覚えています。化学の中山先生は当時「昆虫採集」という選択授業を開講されていて、当時から昆虫が好きだった私が受講したところなんと生徒が私一人だったため、マンツーマンで昆虫採集と標本作成の方法を教えていただきました。
高校卒業後はICUに進学し、生物学を専攻しました。卒業研究ではキタキチョウの翅の模様形成について調べたので実験対象のキタキチョウを入手する必要があり、主にICUキャンパス内で採集していたので、虫取り網を持って広いキャンパスを一人であちこちウロウロしていた思い出があります。
その後は都内で国立大の修士課程に、博士課程でカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)に進学し、サンディエゴで約5年半の研究生活を送りました。博士研究のテーマは線虫という大きさ約1mmの線型動物を利用して、「興奮性と抑制性の神経活動バランスがどのように保たれているのか」について分子遺伝学的手法を用いて調べるというものでした。まだ誰も知らない遺伝子の機能を解析するのはとてもワクワクする作業です。線虫と我々ヒトとは進化の上では数百万年も離れていますが、神経細胞の基本的な動作原理は共通しているのが面白いところ。私の研究していた遺伝子も線虫とヒトで似た働きをするものが存在しています。
また、UCSDの1学年上に、ICU高校23期でICU(大学)でも先輩にあたる林磨理人さん(近々シアトルのワシントン大で教員になるそうです)が在籍しており、いろいろと助けていただきました。高校の同期生との再会もありました。高校でクラスメートだった高橋雄宇君を訪ねて彼の勤めるJet Propulsion Laboratoryをおとずれたり、高橋君と、同じく同期で当時サンディエゴに住んでいた上村翔君にUCSDの研究室を案内したり。ほかにも何人かの同期と会って話す機会がありました。どの再会も嬉しく、思い出深いです。
2016年の帰国後からは金沢大学に移り、研究を続けています。もともと私は小さいころから「虫はなぜ、小さな脳しかないのに適切な行動を取れるのだろう?」という点が不思議でした。この疑問を追求して生物学、特に無脊椎動物の神経生物学を学んできたこともあり、現在の研究対象はショウジョウバエ(生ごみの周りで良く見かけられる、いわゆるコバエの一種)です。研究テーマの一つは「ショウジョウバエの記憶メカニズム」。ショウジョウバエの雄は雌を見かけると特定の求愛行動を取り、雌が受け入れると交尾することができます。基本的に、未交尾の雌は雄を受け入れますが、すでに交尾済みの雌は雄からの求愛を受け入れず拒絶します。(雄が求愛拒絶を経験することを、人間の恋愛になぞらえて「失恋」と呼ぶことがあります。)面白いのは、雄は一定時間求愛を拒絶されると(失恋すると)、しばらくの間、新しい雌を見かけても求愛しなくなることです。これは記憶依存の行動変化であることが分かっており、記憶力の低い雄はすぐに失恋から回復して雌に対する求愛を再開するのに対し、記憶力の高い雄では、いつまでも求愛を再開しません。この「失恋記憶」には脳内のドーパミン神経の働きが重要であることが分かっていますが、そのメカニズムの詳細はまだ不明です。私は現在、ドーパミン神経の一部において、ある遺伝子がオンになることによって神経細胞の働きが変化し、記憶の成立を助けているのではないかと考え研究を行っています。この遺伝子はヒトを含む哺乳類にも存在しているため、昆虫と哺乳類の記憶において、まだ解明されていない共通の記憶メカニズムが働いている可能性があり、興味深いテーマです。
ところで、ハエの雄はなぜわざわざ「失恋」を記憶するのでしょうか。すぐに忘れて求愛を再開したほうが効率的に子孫を残せるのでは、と思いませんか。実は「失恋記憶」は、求愛とそれ以外の行動を天秤にかけ、どの行動を優先すべきかを調節する自然の仕組みの一部です。求愛を拒絶する雌が多いということは、「自分の周りの雌はほぼ皆交尾済みである」ことを意味します。そうであれば、求愛行動にエネルギーを使うのではなく、食事や休憩を取り、少し時間をおいてから満を持して求愛を再開する方が、交尾の成功率が高くなる上に長生きできると考えられます。一方、いつまでも失恋の記憶を持ち求愛を再開しないでいると、子孫を残す機会を失ってしまうかもしれません。失恋をどの程度記憶するか、という点について、進化の結果「ちょうどいいレベル」へと調整されているのです。
つい研究についての内容が長くなってしまいました。仕事以外では、修士課程の学生だった頃に知り合った夫と結婚し、しばらくサンディエゴと金沢の遠距離婚生活を送りました。現在は夫婦二人とも金沢大の同じ研究室に勤め、小学1年生を頭に三人の子どもを追いかけながら忙しく過ごす日々を送っています。
次の執筆者として、萩野真実子さんを指定させていただきます。まみこは私と同じく第二女子寮の元寮生で、入学後入寮する日、二人でたまたま同じ時間に寮に着いて言葉を交わしたのが出会いだったと記憶しています。また、どんな切っ掛けがあったかは忘れてしまいましたが、「星歌は言葉を発する時にすごく考えているよね」と言ってくれたのが、口下手な私にはとても嬉しかった思い出です。あれからもうじき25年が過ぎようとしているとは信じがたいですが、会えば当時のように話せる友人です。では、よろしく!