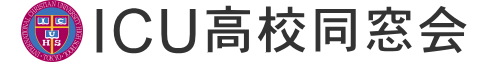高校時代はいわゆる帰宅部でした。授業でも行事でも目立った活躍はせず、休み時間は図書室に籠るか廊下で友人たちとダラダラ過ごすだけ。正直、高校生活そのものへの思い入れも強くありません。そんな僕が22期のエッセイリレーのしんがりを務めていいのか…そう思いながらも引き受けました。今でも年に二回は顔を合わせる旧友の一人である河野君の依頼とあれば、断るわけにはいきません。
僕は哲学を学んでいます。ICU高校のあの図書室でたまたま手に取った本を読んで、自分が日頃考えていることが「哲学」と呼ばれる学問であることを知ったその日から、哲学の道を志してきました。今ではそれを生業にしつつあります。専門は近代ドイツ哲学、いわゆるドイツ観念論です。
もちろん、初めからこのような人生の道筋を思い描いていたわけではありません。大学卒業後は、3年ほど小さな運送会社に勤務していました。普通自動車の免許すら持たずに入社し、屈強なトラックドライバーさんたちと過ごす日々は新鮮そのものでした。まったく縁のない世界でがむしゃらに働いた経験は、今でもかけがえのないものです。しかし、週末に開催していた読書会である哲学書に出会い、これを読み解くためなら生涯を賭けてもいいと思ってしまいます。一方で、とてもフルタイムで働きながら読めるような代物ではなかったため、悩んだ揚げ句、会社を退職し、大学院に入学。修士課程と博士課程には合わせて10年ほど在籍して、博士の学位を得ました。現在は、非常勤講師として都内の私大の授業を掛け持ちしながら、若手研究者を養成する文科省の外郭団体に研究員として採用されています。主に夜勤のアルバイトで生計を立てながらの研究生活は、当然ながら楽ではありませんでした。それにもかかわらず、ここまで来られたのは、ひとえに家族の理解や周囲の応援のおかげです。現在の職も決して安定したものではありませんが、充実した形で哲学の教育と研究に携われることに感謝しない日はありません。
こう述べると、「夢が叶ったこと」を祝ってくれる方もいます。しかし、僕としては何か自己実現や社会的成功を目指していたつもりはありません。正直に言って、こう生きるしかなかっただけです。最近亡くなった敬愛する老哲学者は、「哲学する」具体的なあり方は、教壇に立つか、文筆活動をするか、あるいは、生きることそのものであるかだと語っていました。この三択でいうと、僕自身は明らかに三つ目の道を歩もうとしていました。それゆえ、仮に研究者や教育者という仕事に縁がなかったとしても、何らかの形で哲学的に生きようとしたことに違いはなかったでしょう。それは、修業するとか悟りを開くといった大仰なことではありません。哲学はすべての物事の根本を探究する学問ですが、それを自分の人生においても遂行する。ただそれだけの話です。
思い返すと、こうした生き方の原点はやはりICU高校だったと言えるかもしれません。それは、前述したような、高校の図書室で哲学に関する本を読み始めたという意味ではありません。ちょうど高校時代の後半に、自分が世界の中でどこに位置し、どう生きるべきか、どう行動するべきかという問いを突き付けられ、自分自身の生に初めてきちんと向き合おうとしたからです。きっかけの一つは、「アメリカ同時多発テロ」とその後の「対テロ戦争」でした。それまでも僕は、「社会問題」に対して真っ当に興味を持つ、いわゆる「模範的」な生徒だったと思います。しかし、そんな自分が、現実に起きた世界史的な出来事をどう受け止めたらいいか分からない。いろいろ真面目に取り組んできたつもりが、結局、高校生向けに用意された教科書の中の世界で満足し、足下にある現実の世界を見ていなかったのではないか、そんな疑いが生じてきます。それは、無自覚に前提していた価値観や世界観がまさに崩壊していく過程であり、そこから自分の生と認識を組み立て直すことになる出発点でもありました。
もう一つの原体験を挙げましょう。ICU高校は自由な校風で多様な生徒が集まっているとよく言われます。なるほど、理不尽なほど厳しい校則はありませんし、帰国子女が多数を占めているために、いわゆる同調圧力的文化は希薄だと言えるかもしれません。しかし、少なくとも社会的な観点から見れば、多様であるどころか、一部の比較的裕福な階層の子弟が集まった特殊な学校です。全国津々浦々に文字通りさまざまな境遇の10代がいることを思えば、むしろ画一的な環境であり、謳われる「自由」もそのような条件付きで成り立つものにすぎません。しかし、僕がICU高校に通えて何よりもよかったと思えるのは、同時にそうした事実に向き合い、考えさせられる環境でもあったことです。特に担任だった国語科のK先生、現在は福島で訪問看護ステーションを運営しているH先生、卒業後も研究会でご一緒したN先生といった方々との対話からは多くの大切なこと、しかも哲学の核心にも通底するような事柄を学びました。こうした先生方と出会っていなければ、僕の高校生活は、その後の人生を、少なくとも自覚的な仕方で左右するものにはなっていなかったでしょう。
かなり独特な思い出話を語ってしまいました。もっとも、齢40を迎えつつあるかつての同級生たちは、すでに人生のどこかで同じような自分自身が問い直される経験をしているだろうと思います。また、そうした経験の実感が薄れて、ルーティン化した労働と消費と生活のアマルガムに倦み疲れている人たちもいるでしょう。僕自身、哲学に携わる者としてこうした問い直しは欠かせないと考えているものの、毎日の単調な暮らしに飲み込まれてしまうことも少なくありません。そうした中、あえて高校時代をふり返ることは、自らの原点を見出し、そこから自分の現在地と将来の方向性を照らし出す一つのやり方なのかもしれないと思わされました。その際、高校生活がいわゆる「キラキラしたもの」であるかどうかは関係ないでしょう。自分の生と世界を色褪せさせないものは、出来上がったものとして外から与えられることはなく、自分が歩んできた道程の中に自ら見出すしかないだろうからです。