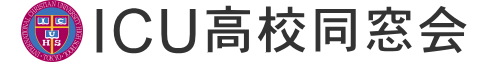32期の山田英輝です。アーチェリー部つながりで、水野賢人君よりバトンを頂きました。拙文ですが、ご笑覧ください。
過去を掬う未来
今、目の前に足の形をした木型が置かれている。これは靴を作るための木型だ。だが、どうやらこの木型は一般的に想像されるような足の形をしていない。強い変形があり、足首から大きく曲がっているもの、外反母趾で大きく親指の付け根がせり出しているもの、強度の偏平足、あるいは足趾が切断されているものと様々ある。これらの木型に革を吊りこみ、靴を作るのだ。時に特殊な素材を用い、症状に対して適切な処置をとり、その強い変形や症状に合わせた靴をつくる。
私の今日の仕事は、この木型の底にコルクの中敷きを作り、透明のプラスチック素材を熱で温め木型にかぶせ、プラスチックの靴を作ることだ。これは、この木型で靴を製作する前の中間チェック、つまり仮合わせ用の靴だ。透明なので、患者さんが履いた時に中の様子が見える。もし圧迫されている箇所があれば、木型のその部分にコルクや石膏を継ぎ足して、実際に作る際にはもう少しゆとりが出るようにする。
コルクを切り出し、熱して真空成型機で圧着する。そうすると、足の裏の形状にきれいに沿った中敷きの上面ができる。底面を靴の形状に研磨機で削り出せば、チェックシューズの仮中敷きのできあがりだ。中敷きができたら今度は、プラスチックの素材を真空成型する。
私は今、ドイツで靴職人の見習いとして働いている。私が作っているのは、足に疾患があり、通常の靴では生活できない患者さんのための靴である。これらは医療用の靴、「整形靴」と呼ばれる。私の職業は、ドイツの医療職「オートペディ・シューマッハー」である。医療技術者としての靴職人、ということになる。勤務先は「医療・福祉用品店」である。ドイツでは、足に疾患がある患者さんの場合、医師が整形靴の処方箋を書き、保険でオーダーメイドの靴を処方することができる。患者さんはその処方箋を持って、マイスターの経営する「ザニテーツハウス」と呼ばれる私たちの医療用品店に来店するのだ。
高校時代の私を知る人なら、私が足に障害を持っていることを覚えているだろう。正確には、「脳性麻痺」による体幹障害だ。それゆえ子供のころから、装具としての靴を利用していた。整形靴との出会いは6歳のころだ。地元の名古屋の障害児療育センターで療育を受けていたのだが、主治医の対応に母は疑問を持っていた。当時、確かに私は歩行に不安はあったものの、自分で歩くことができた。にもかかわらず、主治医は車椅子の製作を勧めたのだった。その医師に強く不満を持った母は、セカンドオピニオンとして代替医療を探した。その一つが、整形靴だった。
当時、名古屋の靴店に、ドイツから来た整形靴マイスターが定期的に指導に来ており、「マイスター相談会」を開催していた。私は整形靴にここで出会った。熊のように大きなドイツ人は、私の足を見て、歩き方を観察した。採型をし、専用の既成品に加工を施した。この経験を私はいまだに覚えている。
この靴があったからこそ、私はいろいろな所へ行くことができた。父の仕事の都合で、海外へ行くことが多かった。インド、タイ、シンガポール。この靴が世界中に連れていってくれた。たとえば、私が杖や車椅子を利用していたとすれば、もしかすれば父の赴任に帯同せず、日本にそのまま居たのかもしれない。シンガポールでの優秀な友人たちとの出会いも大きな刺激になり、地元に帰るのではなく、友達も受ける東京の高校も受けることにした。ICU高校との出会いは、そんなシンガポールでの暮らしにある。そして、間接的にではあるが、その機会を与えてくれたのは他でもない整形靴だった。
しかし、私は長い間この靴を愛せなかった。自分にとって、この靴は常に自分の障害の象徴になっていた。色は白か黒かしか選べず、日本の保険制度では1年半に1足しか支給されなかった。いつもボロボロで、重たく固い。この靴は「不自由」の象徴だった。本当はこの靴は私にたくさんの自由を与えてくれた「自由」の象徴だったはずなのに、これを愛することができずにいた。
大学に入り、アキレス腱を延長する8時間に及ぶ大手術の末、麻痺の症状は大きく改善した。そのあとは、整形靴の着用は必ずしも必要ない状態になった。私はやはりもう履きたくはなかったし、退院後、保護のための装具が外れると、真っ先に向かったのは、なんでもない「ABCマート」だった。そこで買ったのは、どこにでもあるようなコンバースである。私にとってはただそれが憧れだった。
ただ、手術をしたことで、私の障害はなくなったわけではない。事あるごとに、自分の障害が後ろから追いかけてくる感覚を覚えた。どうしても逃げ切れなかった。時折起きる腰痛。些細なことで「できない」に直面する。
それからしばらくして、腰痛にやはり不安を感じたので、およそ5年ぶりに整形靴店を訪れ、久しぶりに整形靴技術に触れた。この時はじめて、整形靴技術というものに衝撃を受けた。自分にとって当たり前にそこにあったものの素晴らしさに気づき、やっと肯定的な物として受け入れられるようになった。偶然、その夏、母が整形靴店の求人を見つけ、冗談交じりで「こんな求人もあるよ」と見せてくれた。大学院生だった私はいろいろに悩んでいた時期だったのだが、その求人が最も魅力的な進路に感じられた。
その選択は、「すべてを貫き解決する」唯一の選択に思えた。自分の人生に与えられた理不尽な困難を、大嫌いだったものを、不自由の象徴だったものを、唯一、「自由の象徴」に塗り替える、逆転の切り札に見えた。自分の人生すべてを1本の串で貫き通すことができる確信があった。
それから3年、私は日本の整形靴店で勤務し、基本的な技術を習得した。ドイツに行くということを決めたのは最初の1年目だった。このために生きる、という確信があるからこそ、迷いはなかった。やるなら自分の人生賭けるくらい、真剣にやろうと思った。
今、私はドイツで整形靴のマイスター資格を目指して修行している。日本人ではいまだ10人いるかいないか、非常に貴重な資格である。まさか、30近くにもなって新しくドイツ語を勉強して、海外で苦学生をやるとは思わなかったが、世界中で活躍する友人たちの姿も私の背を押している。あたりまえに自分のしたいことをしてもよいのだ、という風土の中育ったのは、自分にとって宝のような経験であり、だからこそ、いまこの死に物狂いのチャレンジに挑戦できている。